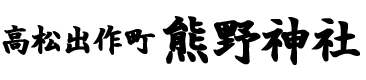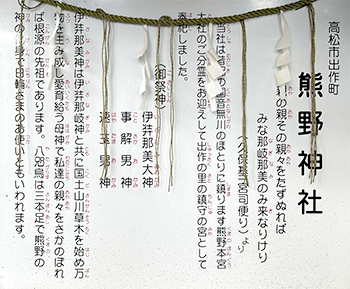 かつては、日本の神道と仏教が融合した神仏習合思想の一つである本地垂迹(ほんじすいじゃく)説により、神は仏の仮の姿とされ、仏や菩薩(ぼさつ)が人々を救うため、仮の姿をとって現れる「権現」という言葉が神号に使われていました。
かつては、日本の神道と仏教が融合した神仏習合思想の一つである本地垂迹(ほんじすいじゃく)説により、神は仏の仮の姿とされ、仏や菩薩(ぼさつ)が人々を救うため、仮の姿をとって現れる「権現」という言葉が神号に使われていました。
このため、熊野神社は、熊野三山(熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社)に祀られている神々を称する熊野権現と呼ばれることもあり、これに倣って当社も「出作権現」として親しまれた時期があったようです。
明治維新後は、神道の復興により熊野権現は正式に熊野神社と改称されました。
当社も、明治元年(1868年に)現在の社号「熊野神社」に改称し、村社とされました。
他方、幕末から明治維新の頃にかけては衰退が酷く、幣殿及び拝殿も狭隘で村里の一小祠に過ぎなかったようです。
明治2年(1869年)に、神仏分離令(1868年)を受けて調査が行われました。「御神体を確認したところ、長さ一尺三寸ほどの立像―女体の像であったが、一つは小さい仏像だったため、これを取り除いた。」と記録が残っています。
その後、明治9年(1876年)5月から、社殿の再建修復が行われました。
まず、本殿敷地の地上げが実施され、日山石による高さ三間の石積みが築かれた上に本殿が安置されました。幣殿・拝殿は拡張され、旧拝殿は西脇に移設されました。
馬場の中央から南方向へ五十七間、幅三間の土地を参道用に購入し、南側道路まで接して、その東側には四十坪の土地を御旅所としました。
当社は、この再建修復により現在のような姿になったと考えられます。
また、現在は残っていませんが、明治44年(1911年)には神楽殿と離宮が新築された記録もあります。